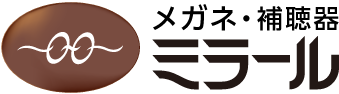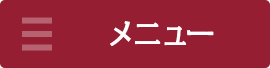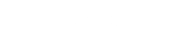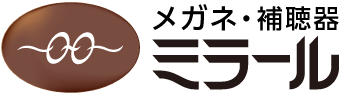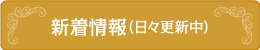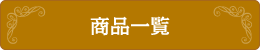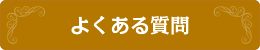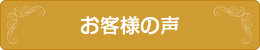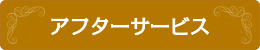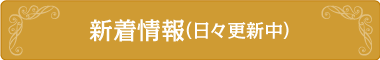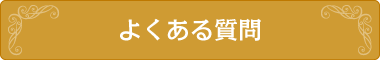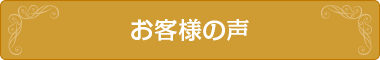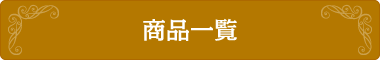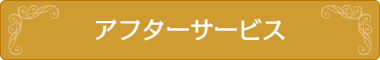認定補聴器技能者のブログ『補聴器通信』 骨導式補聴器① 東武百貨店5階 補聴器さろん
2024.6.17 池袋東武店, 補聴器通信, 補聴器

東武百貨店池袋店5階10番地 補聴器さろんの豊川です。いつも当店をご愛顧いただき、ありがとうございます。
こちらのコラム『補聴器通信』では、イベント情報とは別に、聞こえや補聴器のお役立ち情報を配信いたします。
不定期ですが是非お読みください。
骨伝導式補聴器①
昨今、聞こえに関する製品「ヘッドフォン、イヤホン、補聴器等々」は発達を続けています。
その中で「骨伝導式」という言葉を目にする機会が増えてきており、補聴器販売の現場でも問い合わせが増えております。
今回は2回に分けて、骨伝導式補聴器についてお話しさせていただきたいと思います。
補聴器の種類
補聴器の種類には「気導式」と「骨伝導式」の2種類があります。
補聴器には耳穴に補聴器もしくは、補聴器に接続されたイヤホンを差し込んで聞く「気導式」補聴器。



音の伝達経路:外耳→中耳→内耳(蝸牛)→聴神経→脳
耳穴にはなにも挿入することなく、一定の部位に補聴器を当てることで聞く「骨伝導式」補聴器。


音の伝達経路:側頭骨(頭がい骨)→内耳(蝸牛)→聴神経→脳
普段、ヒトは「気導音」と「骨導音」を合わせて聞いています。
ボイスレコーダーに録音した自分の声がいつもと違って聞こえるのは「気導音」だけを聞いているからです。
耳の穴を塞いで周囲の音を聞こえにくくしても自分の声は大きく聞こえるのは「骨導音」を聞いているからです。
一口に難聴と言っても音を伝える部分のどこに問題があるか?で種類が分かれます。
骨伝導式補聴器が効果を発揮する方は伝音性難聴の方です。
それでは、難聴の種類についてお話しをさせていただきます。
難聴の種類
難聴には、伝音性難聴、感音性難聴、混合性難聴の3種類があります。

耳介で集音(外耳)→鼓膜、ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨(耳小骨)で音を増幅(中耳)→蝸牛で音を電気信号に変換(内耳)→聴神経を経て脳で認識(後迷路)という流れでヒトは音を理解しています。
音を集め、増幅する外耳、中耳に何か問題があるのか?増幅された音を判断する内耳以降に問題があるのか?で難聴の種類が変わります。
伝音性難聴
音を集音する、増幅する経路=外耳又は中耳に何か問題が有り、聞こえが悪くなっている難聴。
耳垢が多く溜まってしまっている耳垢栓塞、慢性中耳炎、滲出性中耳炎、鼓膜穿孔、耳小骨の動きが鈍化する耳硬化症、耳小骨の損傷等が原因で内耳へ音を大きく伝えることができない為、聞き取りが低下します。
音が「ハッキリしない」というよりは、そもそも音が全て「聞こえない(小さく聞こえる)」といった印象です。
医学的に治療可能なケースがあり、治療を行えば補聴器を必要としない場合も有りますし、完全回復が見込めなかった場合、補聴器の検討を考えます。
音を大きくすることが苦手な難聴なので、単純に音が大きくなればある程度聞こえるという方が多いです。
伝音性難聴の聴力図の例

「〇」が気導聴力。耳穴→鼓膜→蝸牛で聞こえている音
「<」が骨導聴力。側頭骨に直接音の振動を加え、内耳を刺激して聞いている音
骨導聴力が悪くないのに対し、気導聴力が悪くなってしまっている状態。
感音性難聴
外耳・中耳で増幅された音を感じ取る内耳もしくは聴神経・脳の何かに問題が有り、聞こえが悪くなっている難聴です。
先天性難聴、突発性難聴、加齢性難聴、騒音性難聴、メニエール病等が具体的な症例となります。
伝音性難聴とは違い、「聞こえる音」「聞き取りにくい音」に分かれます。
音が「ハッキリしない」「聞き間違う」といった印象です。(特に加齢性難聴の場合)
突発性難聴やメニエール病等急性に起こる難聴に関しては、治療により回復の可能性がありますが、多くの方が該当する加齢性難聴等の慢性的に生じている難聴については治療が困難とされています。
これは音を感じ、電気信号に変換する蝸牛内の有毛細胞が再生能力を持たずに徐々に劣化、減少。
それを再生するような治療が確立されていないことが原因です。
(*IPS細胞を利用した内耳細胞の作製等の研究は進んでいるとのこと。)
感音性難聴の方は回復が困難の為、予防と早期に補聴器を利用しての聴力リハビリテーションが大切となります。残存聴力が見込めない方は人工内耳の手術も検討となります。
感音性(混合性)難聴の聴力図の例

「〇」が気導聴力。耳穴→鼓膜→蝸牛で聞こえている音
「<」が骨導聴力。側頭骨に直接音の振動を加え、内耳を刺激して聞いている音
聴力が平坦ではなく、音の周波数によって聞こえに差がある
混合性難聴
伝音性難聴と感音性難聴の特徴を併せ持った難聴
先にお話しした先天性難聴、加齢性難聴。その他頭部外傷による感音性難聴。
中耳炎の放置による難聴等は伝音、感音双方の原因になる確率が高いです。
伝音性難聴の症状、感音性難聴の症状がどの程度かによって聞こえは変わってきますが、加齢性難聴の場合は感音性難聴の症状が強くやはり音が「ハッキリしない」といった印象です。
伝音性難聴の症状が強い方は治療で改善も考えられますので、その方の症状に合わせて治療、補聴器の装用等を検討していきます。
まとめ
先にもお話ししましたが、外耳・中耳のみに異状のあるかたには外耳・中耳を使用しない骨伝導補聴器は有効です。
骨伝導式補聴器が大きく効果を認められるのは伝音性難聴の方になります。
一般的に多くの方がお悩みの加齢性難聴については感音性・混合性難聴なので、骨伝導式補聴器の効果を得られにくいです。
次回は骨伝導式補聴器のメリット、デメリットについてご紹介させていただきます。