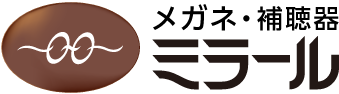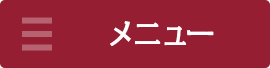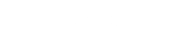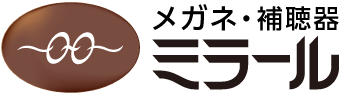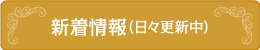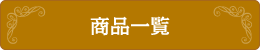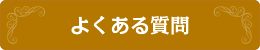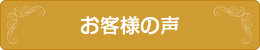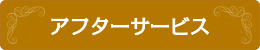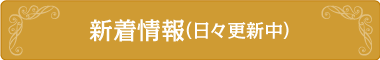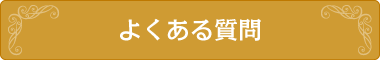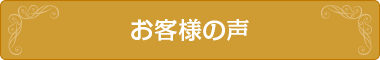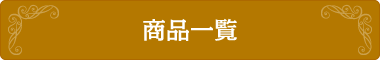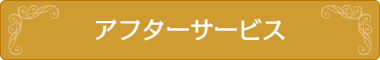他人ごとではない?「認知症と聞こえ」のお話し(その2) 池袋東武補聴器さろん
2018.10.18 池袋東武店, 補聴器通信, コラム

東武百貨店池袋店5階10番地ヒアリングギア・補聴器さろんの豊川です。
昨日に引き続いて「難聴と認知症」についてお話しいたします。
「認知症と聞こえ」のお話し vol.1 どうして難聴と認知症に関係があるのでしょうか?
前回、難聴と認知症に関する研究の一部をお話しさせていただきました。
今回は「何故、難聴になると認知症になるリスクが高くなるのか?」という話をさせていただきます。

 正直なところ、これに関しては絶対的な研究結果は出ていません。
正直なところ、これに関しては絶対的な研究結果は出ていません。
いくつかある仮説について触れたいと思います。
〈共通原因説〉
脳にはたくさんの神経細胞が集まっています。音を聞きとる感覚神経と認知機能を司る中枢神経に同時に影響が及ぶと、同時並行で聴力と認知力の機能低下が起こります。
つまり、難聴があるから認知症になるのではなく、難聴と認知症に共通の原因が作用するという考えです。
〈認知負荷説〉
私たちの脳にはパソコンでいうところのメモリーがあり、「〇〇を行う」と思うと、その分のメモリーが消費されます。
例えば家から出かける前に「財布を忘れたから一旦戻ろう」という行為が一度このメモリーに一時保存されます。しかし、その時ちょうど携帯電話が鳴り出し、外出先の家族から洗濯物を取り込むように頼まれます。この時「財布を忘れたから一旦戻ろう」という最初の記憶が「洗濯物を取り込む」という記憶に上書きされる形で消されてしまい、家の鍵を閉めた時点で「あっ、財布忘れた」となり、再び家に入る。
あれもこれも同時にやろうとした結果、メモリーの容量が不足し起こる物忘れの典型です。
難聴のある人は日常生活で耳から入ってくる情報が少ないため、それを理解しようと無意識のうちに「聴く」ということに対して、人よりも多くのメモリーを消費してしまっていると考えられます。
「聴く」ということに対して、人よりも多くのメモリーを消費した結果、メモリーの容量が足りなくなり、認知機能が低下するという考えです。
冒頭に記した通り、仮説ですので断定はできませんが、いくつかの要因が混在して、認知機能の低下を引き起こす原因になると考えられます。
難聴になると周囲からの情報量が絶対的に減少します。その結果―
[音や声などの聴覚刺激が入らない(情報量の不足)] → [コミュニケーションが困難になる / 危険の察知、周辺環境の把握がしづらくなる] → [心理的、情緒的影響 / 孤立、不安、意欲の減退] → [社会との交流、参加の減少] → [認知機能への影響]
このような影響が出ることが考えられます。
大切なのは、難聴によってすぐに認知症になるわけではないということです。
難聴によってコミュニケーションが少なくなったり、社会交流が減ったりすることで認知機能に影響が出る可能性があるということです。
では、難聴とはそもそもどういうものなのでしょうか?
次回はその点をお話ししたいと思います。